文:尾形聡子

[photo by Felipe Bustillo]
猛暑が続く今年の夏。思うように散歩に出ることもできず、愛犬の運動量をどうやって維持しようかと悩んでいる飼い主さんは多いでしょう。当然のことながら、あまり動かずにいつもと同じように食事をしていたら…体重増加は免れません。それは犬だけでなく人も同じ。ですが、太りやすさというものに個体差があるのも犬も人も同じです。
太りやすさや太りにくさの個体差には、遺伝的な要因と環境的な要因の両方が影響を及ぼします。
たとえば遺伝要因として、食いしん坊犬種の代表ともいえるラブラドール・レトリーバーはPOMC遺伝子の変異が肥満と関係していることがわかっています。何でも丸呑みしてしまうようなラブの行動に科学的な裏付けがされたのです。このPOMCという遺伝子に変異があると、食欲が増すだけでなく、空腹感の強さやカロリー消費の低下も招いており、適正な体重を維持するのがとても難しい状態に置かれるかもしれないというのです(詳細は「ラブを太りやすくさせる遺伝子変異、強い空腹感と消費カロリー低下の二重苦を引き起こす」参照)。
そもそも基礎代謝量は個体差があり、犬種や骨格、筋肉量によっても異なります。加齢により筋肉量が減っていけばその分基礎代謝量をも低下していきます。
一方で、環境的な要因といえば、散歩や遊びなど日常的な運動量、食事量やおやつの与え方などが挙げられます。基礎代謝に対して運動量が少なくたくさんエネルギーを摂取し続ければ太るのは当たり前のことで、誰もが知ることでもあります。それでもなかなか体重の管理がうまくいかないのが人の常。
ですが、太り過ぎは関節炎や糖尿病などさまざまな病気にかかりやすくするばかりか、寿命を短くしてしまう可能性もあるのです。
人の肥満と同様に犬の半数以上が太りすぎだと報告のあるアメリカ。健康問題を脅かすこの事態を見過ごしてはならないと考えたテキサスA&M大学の研究者が主導する研究チームでは、犬が太る背景にある理由を詳細に調査しました。

[photo by Brett Jordan]
食欲の強さは犬種で異なっていた
研究者らは、犬の食べ物に対する動機づけの強さ(Food Motivation Scores:FMS)と飼い主の食事管理をする強さ(owners’ feeding management scores:OMS)をスコア化し、それと犬の体の状態(ボディコンディションスコア;BCS)との関連性を評価しようと考えました。
犬の食べ物に対する動機づけの強さのスコアは、犬の食べ物への反応性、満腹感の持続、好き嫌いの程度、食べ物への関心などについての質問票を、飼い主の食事管理のスコアは食事量の管理、おやつの管理、体重を管理するための運動などについての質問票に飼い主が回答する形で算出されました。
使用された質問票のデータは2019年から2021年にかけて「Dog Aging Project」に登録された13,890頭の犬についてのもの。Dog Aging Projectとはアメリカ国立老化研究所がサポートする大規模研究で、犬のライフスタイルや環境が犬の老化にどのように影響するかを理解するために2019年から開始されました。Dog Aging Projectに蓄積されたデータを利用した研究については、「愛犬のご飯は1日何回がいい?」など、犬曰くでもこれまでにいくつか紹介していますので、ご興味のある方は以下のリンクから記事をご覧ください。
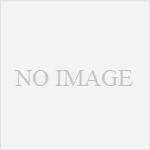
これらのデータを解析した結果、食べ物に対する動機づけのスコアは、アメリカンケネルクラブによる7つのグループ分類において、スポーティング・グループの犬種(ラブラドール、ゴールデンなどのレトリーバーやスパニエル、ポインターなど)がもっとも高く、そのノンスポーティング・グループの犬種(ブルドッグ、プードル、ボストン・テリアなど)がもっとも低いことがわかりました。
また、多頭飼育をしている場合、一頭だけで飼育されている犬よりも食べ物への動機づけスコアは高いことが示されました。これは「相手に取られまい」とする行動のあらわれだと考えられます。
さらに都市部の犬の方が田舎暮らしの犬よりも食べ物への欲求が強く、これは日々の運動やストレスレベルが食欲の強さに影響をしている可能性があるかもしれません。
食事管理スコアが高かったのは?
意外なことに、太っている犬の飼い主の方が食事管理のスコアが高い結果となりました。食事やおやつの量を減らしたり、運動を増やしたりする傾向があるのになぜ犬が太っているのでしょうか。
本来であればそのような制限や運動の機会の増加は肥満予防となるはずなのにそうではなかったのは、食事管理をするのが犬の体重が増えた後に始まったためです。それは人でも同じでしょう。適正体重を維持しようと頑張っている人も一部にはいますが、多くの場合、太ってから運動やカロリー制限を始めるものです。
200頭の犬における肥満度の評価では、飼い主の評価と獣医師の評価との間でおよそ4人に1人の割合(24%)で評価が一致していませんでした。食い違いの評価の多くで飼い主は、太りすぎの犬を標準体型だと評価していました。
愛犬の健康状態を現実的にとらえず、「このくらいの方が健康的」「これが普通だ」というように過小評価してしまうのは、それぞれの犬種や個体に適切な体重がどのくらいであるべきかを知らない可能性があります。さらに、犬への愛着が子どもの肥満と同様に「ぽっちゃりしている方が健康的でかわいい」と信じたい気持ちにさせてしまうこともあるかもしれません。あるいは、毎日見ていると変化に気づきにくく、いつの間にか太ってしまってもそれが「普通」に思えてしまう可能性もあるでしょう。
また、影響を受けるかもしれないのが周囲の犬やSNSからの影響です。よく目にする犬たちが皆ぽっちゃりしていたら、それが「標準体型」と思ってしまうかもしれません。似たような例としては短頭種のいびきが挙げられます。短頭種の多くがいびきをかくのだから、うちの子がいびきをかいても「普通」だと思ってしまい、抱えている健康問題に意識が及ばなくなってしまうというものです。


[photo by Nii SHU]
食いしん坊の愛犬をぽっちゃりさせないために
太ってから痩せることがいかに大変かは、誰もが想像に難くないことでしょう。愛犬に健康的な体型を維持して欲しいのであれば、なにより「太らせない」ように管理することが大切です。
遺伝的に太りやすいことが明らかになっているラブラドールだけでなく、犬種が違っていても、飼い主目線で「太りやすいかも?」「食に対する要求が強いかな?」と愛犬に感じるのであれば注意が必要です。なぜなら肥満には複数の遺伝的な要因が関与していると考えられており、それが犬でも少しずつわかり始めているからです。

満腹感を与えるには、スニッフマットやパズルフィーダーのようなものを使うこともできるでしょう。食事にありつくために犬は頭を使い、採食本能を満たしつつ、食べるスピードも遅くなります。それについての解説は以下の藤田さんの記事をぜひとも参考にしていただければと思います。

さらには、おやつの使い方を工夫することでも与えすぎを防ぐだけでなく、犬とコミュニケーションをとる機会も増えて一石二鳥。さらにはトレーニングも活かすことができて一石三鳥!

すでに愛犬がぽっちゃりです…という方にはこちらの記事を。ひとりではなかなか続かないのがダイエットというもの。犬友といっしょに始めてみるのもいいかもしれません。

そして飼い主さんの意志の強さも大切です。おねだりされてもすぐにおやつを与えない、そんな強い心が必要とされます。家庭犬として生活を送る犬の体重の管理はすべて飼い主の手中にあるようなものです。しかし、「美味しいおやつをラクして食べたい」傾向は、ぽっちゃり体型の人と犬とでそうやら共通しているようです。

愛犬の健康のためには、ときに心を鬼にすることも飼い主の役目。適正体重を維持できるよう、あるいはちょっと体重を減らせるよう、大いに工夫して楽しく取り組んでいけるといいですね。
【参考文献】


