文と写真:藤田りか子
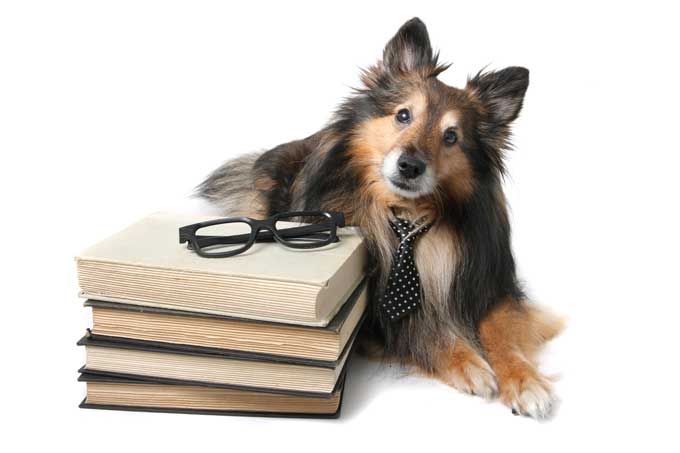
[Photo by GVictoria]
むかーし、私が小学生の頃(だったと思うのだが)、教室内でよくあったジョークで
「ヒマラヤって10回言ってみて」
というのがあった。ヒマラヤ、ヒマラヤ、ヒマラヤ…と律儀に言われた通りにやったのち、
「世界一高い山は?」
と質問がくる。そこで即「ヒマラヤ」と答えてしまい、
「ブー!エベレストでした!」
と引っ掛けられるのである。そうだよね、エベレストに決まっているじゃん!と頭をポリポリ。記事「『この人は犬のトレーニングに成功するぞ!』を予想する」で紹介した認知反射テスト(Cognition Reflection Test) が得意と話してくれた犬曰くのライター、臨床心理士の北條美紀さんなら、こんなジョークには子供の頃から引っ掛からなかったと思うのだが、私は見事相手の思惑通りにミスを犯した。
「ヒマラヤ、ヒマラヤ….」は子供同士のジョークではあるが、これって今よく考えてみると、「認知コントロール」をチェックされていたのではないかと思う。認知コントロールとは、課題を正しく遂行するために、無関係な思考や刺激を無視する能力のことだ。我々人間が日常生活するうえで重要な役割を果たしている。その場ですぐに判断が求められたり,行動を切り替えたり,やめたりすることに関係しているからだ。いわば、よりよく生きるために必要な能力ともいえよう。
認知コントロールは、もちろん犬にも備わっている能力だ。そして、このコントロールが高い犬ほど、家庭犬として暮らしやすいと私は思う。なぜなら、周囲の刺激に振り回されにくく、こちらの指示に注意を向け続けやすいからだ。
たとえば散歩をしているときに、向こうから他の犬がやってきたとする。向こうの犬はガウガウ状態で、すれ違う際はできるならこちらとしてはすみやかにスルーしたい。こんなとき、愛犬の名前を呼びこちらに注意を向けてもらう。犬は飼い主の顔をみるだろう。そうすることでガウガウ犬と視線が合わず、余計な刺激や挑発につながりにくくなる。
しかし認知コントロールが悪い犬であれば、「こっちを向いて!」と呼びかけても、とっさの判断ができず、つい刺激の方向、つまりガウガウ犬のほうへ目が行ってしまうだろう。
さて、今や8ヶ月齢となったうちのちびっこ、ラブラドールのシャチにはこの認知コントロールがどうも上手く機能していないことに気がついた。アシカやミミチャン(先住犬たち、ともにラブラドール)に比べると、すぐにディストラクションへ意識が逸れてしまうのだ。この傾向については、実は彼女が3ヶ月齢ぐらいになった頃から気になっていたものの
「いや、もう少し大きくなったら、うまくできるようになるだろう」
と楽観的に構えていた。しかし一向によくならない。これはあえて鍛えたほうがいいかもしれない。認知コントロールが弱いのであれば、早めに介入して向上をさせる!そこで、彼女に簡単なタスクを教えることにした。
認知コントロールタスク
このタスクは台所でもできる簡単なものなので、ぜひみなさんも試してほしい。課題は、目の前に置かれたトリーツではなく、自分の後ろにあるトリーツを優先して取りに行く、というものだ、
犬であれば、当然見えている食べ物の方を先に取りたいはずだ。しかし、この課題ではあえてその衝動に逆らってもらう。私が「うしろ」と声をかけたら、シャチは目の前の誘惑には手を出さず、一度思考を切り替え、指示通りに後ろへ向かわなければならない。目の前のトリーツはあくまでディストラクション(注意をそらす刺激)。それに惑わされず、適切な判断と行動ができるかがポイントとなる。
とはいえ、このタスクではいきなりディストラクションを導入するわけではない。まずは、「うしろ」のコマンドを理解してもらうことから始める。
手順
1. スタートのポジションをつくる
犬といっしょに歩き、トリーツの入ったボウルを地面に置く。ただし、すぐには食べさせない。そのボウルを後にし、いっしょにさらに5歩き、犬に座ってもらう。ハンドラーは犬と向かい合う形で立つ(下写真参照)。
2. 衝動を抑える練習
犬は当然、後ろにあるボウルが気になって仕方がない。しかしここでは、まず「すわれ」の状態を維持してもらう。ハンドラーは「ストップ」と声をかけ、犬とアイコンタクトを取る。犬はおそらく後ろを振り向き、ボウルに視線をむけようとするかもしれない。しかし、ここで重要なのは ボウルではなく、人間に視線を戻せるかどうか…?

(写真上)犬は正面に座っている状態。犬の後にはトリーツの入ったフードボウル。

ストップ!というこちらにアテンションを向けてもらうコマンドを出す。この時に犬が後ろのフードボウルを気にして、後ろを向いているようであれば、まだコマンドを出してはだめ!
3. コマンドを実行してもらう
犬がこちらの目を見ることができたら初めて、「うしろ!」とコマンドを出し、「いいよ!」と解放の合図を出す。そこで初めて、後ろのトリーツを食べに行くことが許される。
注1:もし犬がどうしても座り続けてくれなかったら、だれかにリードを持ってもらい、後に行くのを阻止してもらうこと。
注2:もし犬が勝手に後ろへ行ってトリーツを食べてしまう場合は、アシスタントを用意しよう。犬が後へ動き出した瞬間、アシスタントがボウルをさっと持ち上げ、食べられないようにする。これにより、「指示なしでトリーツに向かうと手に入らない」というルールが明確になる。

「うしろ!」という許可を出す前に、犬がフードボウルに向かっていってしまった場合はすかさずアシスタントの人にそのフードボウルを取ってもらうこと!
4. ディストラクションの導入
3をコンスタントにこなすようになったら、次は、ディストラクションを置く段だ。完成図としては犬のすぐ目の前に置いて、「うしろ!」のコマンドを出し、ディストラクションを無視して、後にいってもらう。しかし最初は、ディストラクションは犬のそばではなく、ハンドラーのすぐ後に置いておく。目の前の誘惑に釘付けになっても、思考の切り替えができ、言葉に従って行動できるか。これこそが認知コントロールトレーニングのキーとなる。

ハンドラーの後にもフードボウルを置いて、ディストラクションを導入
5. ディストラクションを難しくする
犬が「うしろ」というコマンドの意味を理解し、誘惑の存在があってもきちんと理解できるようになってきたら、次はいよいよ難易度を上げる。このステージでは、ディストラクションをハンドラーのすぐ目の前に置く。つまり、犬の視界の真ん中に、フードボウルが鎮座することになる。ここで犬に求めたいのは、衝動のまま目の前の誘惑に向かって動くことではなく、「指示を聞いてから動く」という選択を、自らの力でできるようになることだ。
手順としては前述したものと同じだ。犬は座りハンドラーは正面に立つ。そして犬の背後にはフードボウル、そして、犬の目の前にもトリーツのはいったフードボウル。
まずは落ち着いて「ストップ」と合図を出し、アイコンタクトを取る。犬が一瞬でもこちらを見ることができたら、「うしろ」とコマンドを出す。犬が視線を前のボウルから切り替え、後方に向けたら、大成功!
「これって単なる服従訓練?」
と思われるかもしれない。確かにそうなのであるが、ここにはたくさんの脳内情報処理の過程が含まれる。犬はこの瞬間、
- 衝動を抑え
- 誘惑を無視し
- 状況を整理し
- 言葉(ルール)に従い
- 正しい選択肢を選ぶ
という、一連の認知プロセスを踏む。「分かっているけど、我慢して、考えて、選ぶ」という、人間の子どもが学ぶ「実行機能(Executive Function)」と同じプロセスだ。
この応用はいくらでもできるのだが、とりあえず今回はこちらを紹介しておくことにとどめておこう。フードボウルではなくとも、おもちゃなども使うことができる。何が愛犬にとっての誘惑なのか、自分で選んでみるといいだろう。
【関連記事】





