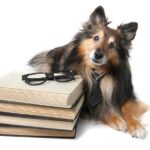文:尾形聡子

[photo by Galina]
犬は雑食である。これは今では広く知られた事実でしょう。植物と動物の両方を食べられるという点では人と似ていますが、その背景には、肉食の祖先であるオオカミから進化する過程で、犬がでんぷんを代謝する能力を獲得してきた歴史があります。農耕の発達とともに人の食生活に穀物が増えると、その環境に適応できる個体が人のそばで生き残りやすかったためだと考えられています。
でんぷんを消化するには、アミラーゼという酵素が必要になります。この酵素を作るのが AMY2B と呼ばれる遺伝子です。オオカミはこの遺伝子を1コピーしか持ちませんが、犬ではコピー数が増えており、より多くのアミラーゼをつくることができます。たとえばディンゴはオオカミと同じく1コピーしか持たないなど、詳しくは以下の記事にもまとめています。

犬種差はあるものの、犬がオオカミより高いアミラーゼ活性をもつことは確かで、これにより食性の幅が広がり、多様な環境へ適応できるようになったと考えられています。一方で、純粋な肉食動物は動物性タンパク質や脂質を効率よく消化する能力に特化しています。
とはいえ、犬も人と同じでアミラーゼ活性には犬種差も個体差も大きく、さらに犬には炭水化物を必ず摂らなければならない、という必須量はないとされています。また、作業犬では低炭水化物・高脂肪食がパフォーマンスを改善するという研究も報告されています(2018年)。
一方で、市販のドライフードの多くは、穀物やジャガイモ由来のでんぷんが多く含まれています。これは単に食材の価格だけでなく、ドライフードを製造する際にでんぷんが欠かせないという技術的理由もあります。
でんぷんは消化されるとブドウ糖になり、体内でエネルギー源として利用されます。ただし、摂取した糖が消費量を上回ると、余ったブドウ糖は脂肪やコレステロールへと変換されます。人の研究からも、精製炭水化物(“白いもの”)は消化吸収が早く、血糖値を急上昇させやすいことがよく知られています。反対に、玄米や全粒粉小麦のような“茶色いもの”は食物繊維や微量栄養素が残っており、血糖の上昇が緩やかになります。
また、肉類は炭水化物をほとんど含まないため、単独で食べても血糖値をあまり上げません。脂質も直接的に血糖値を上げるわけではありませんが、摂りすぎれば内臓脂肪が増え、インスリンの働きを妨げることで間接的に血糖値を上昇させる要因になります。
このように、栄養素ごとに代謝への影響は異なり、犬種や個体差も加わるため、高炭水化物のドライフードと低炭水化物の生肉ベース食とで、犬の健康にどのような違いが生まれるのかはまだ十分に理解されていません。
そこで今回、フィンランドのヘルシンキ大学の研究チームは、両者が犬のエネルギー代謝にどのような影響を及ぼすのかを、血液バイオマーカーと体重の変化から詳しく比較する研究を実施しました。
この研究を実施したのは、以前「アトピー性皮膚炎と食餌の関係、生食それともドライフード?」で紹介したヘルシンキ大学の「DogRisk」という研究プロジェクト(2009年から続けられている、50問で構成される大規模オンライン調査)のチームです。彼らはこれまでもスタッフォードシャー・ブル・テリアを対象として、食餌とアトピー発症の関連を解析してきました。そうした先行研究で得られた基盤データがすでに揃っていたことから、今回の研究でも同じくスタッフォードシャー・ブル・テリアが対象とされています。

[photo by k9arteu from Pixabay]
高炭水化物のドライフードと低炭水化物の生肉ベース食、数ヶ月後に違いはでるか?
研究対象とされたのは、家庭犬のスタッフォードシャー・ブル・テリア46頭です。主に、ブリードクラブの会報やFacebookなどのSNSを通じて募集され、アンケート調査に参加した飼い主の犬たちです。無作為に「ドライフード群(19頭)」と「生肉ベース食群(27頭)」に振り分けられました。
ここで使われたフードは、特別な研究用のものではなく、一般に市販されているものでした。ドライフードはヒルズの「サイエンス・プラン成犬用センシティブスキン(チキン)」、生肉ベース食はフィンランドのメーカーMUSH社の「Vaisto」シリーズから2種類(豚・鶏・ラムのミックスと、牛・七面鳥・サーモンのミックス)でした。
いずれも「これだけで栄養バランスがとれる」として販売されている完全食タイプで、生食は肉・内臓・骨・野菜やオイルなどを含む冷凍フードです。生食2種類のどちらを使うか、あるいは両方を混ぜるかは、たとえば「このタンパク源はうちの犬には合わないかも」といった飼い主の不安に配慮して選べるようにしてありました。
栄養成分をみると、ドライフードは代謝エネルギーのうち半分弱を炭水化物が占める高炭水化物食であるのに対し、生肉ベース食はほぼ炭水化物ゼロで、タンパク質と脂肪が中心の低炭水化物・高脂肪食です。一般に入手できる市販フードの中でも、栄養組成がかなり対照的な組み合わせといえます。
研究では、まず介入前にベースラインの検査を行い、その後、およそ4〜5か月間、それぞれの犬に割り当てられた食餌を続けてもらいました。給与量は、ベースライン時の体重に基づき、メーカーが示す目安量を参考に調整。いきなりフードを切り替えるとお腹をこわす可能性があるため、1週間ほどかけて、以前のフードから徐々に研究用フードへと切り替えるよう指示がだされていました。
介入前後の来院では、獣医師による身体検査に加え、空腹時の採血と体重測定が行われました。採取した血液からは、血糖値、平均的な血糖状態を反映するHbA1c、血糖を下げるインスリンと上げるグルカゴン、中性脂肪やコレステロールなどの血中脂質、ケトン体の一種であるβ-ヒドロキシ酪酸、インスリン抵抗性の指標であるHOMA-IRやTyG指数といった、エネルギー代謝に関わるさまざまなバイオマーカーが測定されました。
これらのデータをもとに、研究チームは、それぞれのタイプの食餌が犬のエネルギー代謝にどのような違いをもたらすのかを統計的に比較しました。

[photo by Mercedes Fittipaldi]
さまざまな代謝指標に違いが見られた
解析の結果、それぞれの食餌タイプにより、血中のバイオマーカーが明らかに違うことがわかりました。
▪️生肉ベース食は血糖を下げ、ドライフードは平均血糖をじわりと押し上げた
4〜5か月の食餌介入を終えたあと、まず明確に違いがでたのが「血糖まわり」です。生肉ベース食のグループでは、空腹時の血糖値が有意に低下しました。一方、ドライフード群では血糖の変化は見られませんでした。さらに、過去数か月の血糖状態を反映する HbA1c はドライフード群でのみ有意に上昇。生肉ベース食では変化がないままでした。
つまり生肉ベース食を食べていた犬たちは、食後の血糖変動に対してより穏やかな代謝状態にあった可能性が示唆されます。
▪️グルカゴンの低下、血糖を上げるホルモンが抑えられた
血糖を上昇させるホルモンであるグルカゴンは、生肉ベース食群でのみ有意に低下しました。生肉ベース食は血糖を上げる方向の力を弱める働きがあると考えられます。
▪️脂質プロファイルは両者できっぱり分かれた
血中脂質は特に大きく異なりました。総コレステロールはドライフード群で上昇、生肉ベース食群で低下、HDL・LDL・VLDL、中性脂肪(トリグリセリド)はいずれもドライフード群のほうが高い値となっていました。
脂質全体として、ドライフード群では上昇方向にあり、生肉ベース食群では下降方向にあるという対照的な構図が鮮明にでていました。
興味深いことに、介入前からドライフードを多く食べていた犬は、すでにコレステロールが高めでした。食餌のタイプが長期的な脂質プロファイルに影響しうることを示唆しています。
▪️ケトン体の上昇、生肉では“軽いケトーシス”に
ケトン体(β-ヒドロキシ酪酸)は両群で上昇したものの、生肉ベース食群のほうが明らかに高いという結果でした。
生肉ベース食は炭水化物がほぼゼロのため、犬が脂肪由来のエネルギーをより使う「栄養性ケトーシス」、つまり糖質が不足した際に脂肪を分解して作られるケトン体をエネルギー源として利用する、生理的な状態に入ったと考えることができます。
▪️インスリン抵抗性の指標はどうだった?
一般的に使われるHOMA-IRには変化がありませんでしたが、もうひとつの指標であるTyG指数は、生肉ベース食で有意に低下していました。
これは近年、人やげっ歯類の研究でもインスリン抵抗性の改善を反映する指標として注目されています。生食の犬では、血糖と脂質(中性脂肪)の両方が下がったことが、この指標に反映されています。
▪️体重はドライ群でのみ増加
体重は、ドライフード群でのみ平均0.53kg増加を示しました。生肉ベース食では変化はありませんでした。
ただし、介入終了時点の体重は両群で同程度であり、「どちらが太りやすいか」の決定的な差ではありません。

[photo by Rebeca Vidal]
長期的な健康への影響を調べる必要性の高まり
今回の研究は、ドライフードと生肉ベース食が犬の体内でまったく異なる方向に代謝を動かすことを、数字の変化として見せてくれました。
生肉ベース食では、血糖や脂質が下がり、ケトン体が上昇するなど、脂肪利用へ代謝の軸が移る反応が見られました。一方でドライフードは、HbA1cや血中脂質、体重が上昇するなど、糖を中心とした代謝の方向へと進む傾向がうかがえます。
しかし、注意が必要なのは、この生肉ベース食は、家庭で手作りするタイプの生肉ではなく、肉・内臓・骨・魚・卵・野菜などをバランスよく含んだ、市販の完全食タイプだったことです。これまでの研究でも、そのような市販の生肉ベースの食餌の摂取は、歯・耳・皮膚の健康状態がいいことや、肝酵素の低下、腸内環境の改善、免疫マーカーの上昇と関連することが報告されており、今回の代謝パターンの違いとも整合しています。
ですが、生食には長年議論されてきた懸念もあります。とくに衛生面のリスクや、手作り生食の栄養バランスの難しさは、獣医師の間で慎重に扱われてきたテーマです。
さらに、この研究はスタッフォードシャー・ブル・テリアだけを対象にしたもので、他犬種で同じ結果になるとは限りません。筋肉量の多い犬種は、糖や脂肪の使い方が他犬種とは異なる可能性があります。また、参加した犬たちは1〜13歳と幅広く、食歴もまちまちでした。生活環境も統一されていないため、代謝に影響するそれぞれの家庭ならではのちがいも含まれています。
そして何より、この研究では 心血管系への影響や長期的な健康への影響は評価されていません。コレステロールの上下が、犬にとってどの程度の臨床的意味を持つのかも、まだはっきりしていません。
つまり、今回わかったのは、「生食がいい/ドライフードが悪い」ではなく、それぞれが犬の代謝をまったく違う方向へ導くという事実そのものです。大切なのは、自分の犬がどんな体質で、どれくらい運動し、どんな消化能力やアレルギー傾向をもっているのかを理解し、そのうえで、どんなタイプの食餌が暮らしに合うのかを考えることです。
食餌選びの正解はひとつではありません。ただ、今回の研究は、犬の体が食べ物をどう処理し、どんな代謝の方向をとりやすいのかを考えるうえで、とても貴重な視点をもたらしてくれるものだと思います。
【参考文献】
【関連記事】