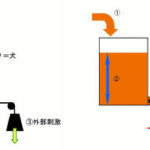文:尾形聡子

[photo by Bram]
遺伝的な原因により生まれつき聴覚や視覚に障がいを抱えている犬がいることは、みなさんもよくご存じと思います。聴覚や視覚の問題は、牧羊犬に多く見られるマールや、ダルメシアンのスポット、グレート・デーンのハルクインなどの毛色と密接に関係していることがこれまでに示されています。毛色をつくる色素細胞は、毛の色のもととなるメラニン色素を産生するだけでなく、正常な聴覚や視覚を持つための働きもしています。そのため、メラニン産生に関わる遺伝子に変異が起こると、同時に聴覚や視覚へも影響が出てきやすくなるのです。そのほか犬の眼疾患には、遺伝的な要因が大きく影響を及ぼす遺伝性白内障や PRA(進行性網膜萎縮症)があり、若齢または中齢で視力を失うケースも少なくありません。
先天性の眼球の形成不全などは見た目にも明らかなことから気づきやすいものです。しかし聴覚に異常がある場合、とりわけ片側だけに難聴がある場合は、生活をともにする飼い主ですら気付かずにいることがあるのも現状です。さらに両方の耳に問題がある場合には、耳が聞こえにくいという健康上の問題を抱えている可能性があるかもしれないと考えるよりも先に、人の言うことを聞かない犬だというレッテルが貼られてしまうこともしばしばです。
では、先天的もしくは後天的に聴覚や視覚に障がいを持つ犬には特徴的な行動がみられるものなのでしょうか。もしみられるとするならば、目や耳に障がいを持つ犬の福祉をどのようにして守っていくべきかという指標ともなるでしょう。
これまでそのようなことについての科学的な調査はほとんど行われてきませんでしたが、アメリカのイリノイ州立大学の研究者らが、聴覚や視覚に障がいを持つ犬と健康な犬との行動の比較研究を行い、結果を『Journal of Veterinary Behavior』に発表しました。