文:尾形聡子
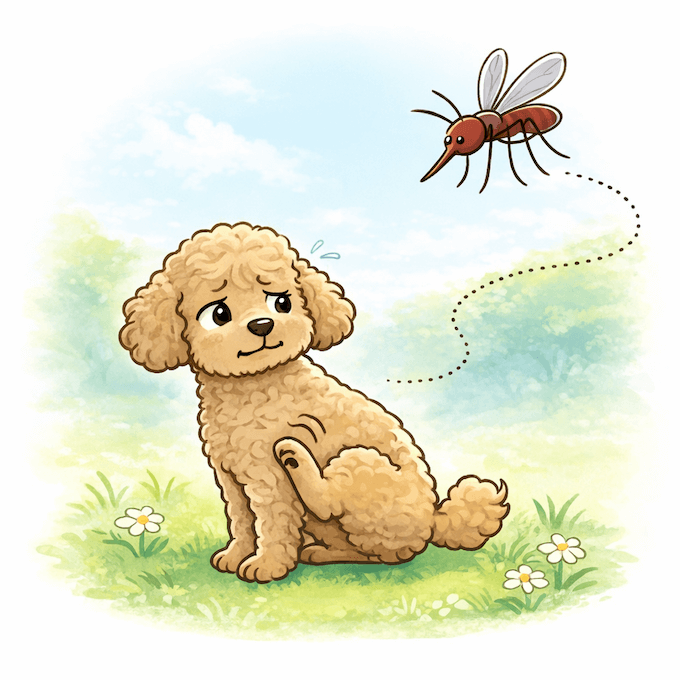
[Illustration by ChatGPT(AI生成)]
年明けも束の間、すでに暦の上では春。これからすこしずつ気温が上がってくると蚊が発生し始めます。犬と暮らしている方にとって、この時期に欠かせないのがフィラリア症の予防です。
フィラリア症は、蚊を介して感染する糸状線虫という寄生虫による病気で、成虫は犬の心臓や肺動脈に寄生します。適切な予防を行わなければ、咳や運動不耐性、呼吸困難などを引き起こし、重症例では命に関わることもあります。
たとえば、忠犬ハチ公の最期については諸説ありますが、その死因のひとつとしてフィラリア症が関与していた可能性があるとされています。ハチ公が生きていた昭和初期には、フィラリアは珍しい病気ではなく、多くの犬にとってごく一般的な死因のひとつでした。当時は有効な予防法がなく、飼い主ができることは限られていたのです。
しかし現在では、フィラリア症は予防薬によって防げる病気になりました。きちんと対策していれば、犬の一生に深刻な影響を与える可能性はきわめて低くなります。この大きな変化は、獣医学と予防医療の進歩がもたらした成果だと言えるでしょう。
一方で、その「予防できるようになった」という事実が、フィラリアを「過去の病気」「たいして心配しなくてもいい病気」と感じさせてしまっている側面もあります。しかし近年の研究は、フィラリアをそう単純には片づけられない存在として捉え直す必要があることを示しています。
フィラリアとイヌ科動物の、思いのほか長い関係
2026年、フィラリア(Dirofilaria immitis)の進化の歴史を、これまでで最大規模のゲノムデータを用いて調べた研究がCommunications Biology 誌に発表されました。この研究を主導したのはオーストラリアのシドニー大学ですが、世界各国の研究者らが参加した国際チームによるもので、オーストラリア、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、中央アメリカなど、複数の地域から集められた127個体の成虫フィラリアの全ゲノムが解析されました。
従来、フィラリアは「ここ数百年のあいだに、人による飼い犬の移動に伴って世界中に広がった寄生虫」と考えられてきました。しかしこの研究により、大陸ごとにフィラリアの遺伝的違いが明確に見られ、近代の人と犬の移動だけでは説明できないことが示されました。
さらに解析結果からは、フィラリアがオオカミやディンゴなどの野生のイヌ科動物とともに、数万年、あるいはそれ以上の長い時間をかけて進化してきた可能性が浮かび上がりました。イヌ科動物の誕生は、人類(約280万年前)よりもはるか以前、およそ4,000万年前までさかのぼります。フィラリアはその過程で、蚊というベクター(病原体を運ぶ生物)とともに、主にイヌ科動物を宿主として安定した生態的ニッチを築いてきたと考えられています。
つまりフィラリアは、人が犬を家畜化してから誕生した病原体ではなく、イヌ科動物の長い進化史の中で共存してきた寄生虫である可能性が高い、ということなのです。
太古から変わらずに生きてきたフィラリアが、変わり始める可能性
興味深いのは、この研究がフィラリアの共進化の歴史を振り返るだけでなく、フィラリアの「これから」にも目を向けている点です。論文の中では、近年の集中的な予防薬の使用、気候変動による蚊の分布変化、犬の国際的な移動などが、フィラリアの分布や遺伝的構造に影響を与えつつあると述べられています。
実際、アメリカの一部地域では、フィラリア側に薬剤耐性が生じているとの報告があります。今回の研究でも、人為的な影響も大きい、近年の地球規模での環境変化が、今後フィラリアの遺伝的な進化をこれまで以上に加速させるかもしれない、と示唆されています。
このことは、単純にこれまでの予防薬が効かなくなるという話ではありませんが、フィラリアが決して静的な存在ではなく、環境に応じて変化しうる寄生虫であることを、あらためて教えてくれる結果だと言えるでしょう。

[photo by kobkik]
「昔の病気」と感じてしまうのは、予防があったから
フィラリア症が、かつて多くの犬にとって一般的な死因のひとつだったにもかかわらず、現在では「予防できる病気」として捉えられるようになった背景には、予防薬の普及があります。言い換えれば、フィラリアが昔の病気のように感じられるようになったのは、病気そのものが変わったからではなく、人が対策を続けてきたからです。
フィラリアの感染は、蚊に刺されることから始まります。犬の体内に侵入した幼虫は、数か月かけて成長し、やがて心臓や肺動脈に到達します。この初期段階では目立った症状が出にくく、感染に気づかないまま病気が進行してしまうことも少なくありません。そのため、発症してから治療するのではなく、感染そのものを防ぐ予防が何より重要になります。
現在使われているフィラリア予防薬の多くは、蚊によって運ばれた幼虫が体内で成長する前の段階を狙って作用するものです。毎月あるいは一定の間隔で投与を続けることで、フィラリアに寄生されるのを防ぐ仕組みになっています。この「定期的に続ける」という点が、フィラリア予防の最大のポイントです。
予防が必要な期間は、地域や年によって変わる
フィラリア対策というと、「〇月から〇月まで」といった目安がよく提示されます。しかし、蚊の活動時期は、地域差だけでなく、その年の気温や天候によっても変動します。近年は春先から気温が高い年や、秋になっても暑さが続く年も増えており、従来の感覚だけでは対応しきれない場面も出てきました。
今回紹介した研究でも、気候変動によって蚊の分布や活動期間が変化し、それがフィラリアの広がりに影響を与える可能性があることが示唆されています。そのような背景を考えると、「毎年なんとなく同じ時期に始める、同じ時期に終える」のではなく、その年の状況に応じて、かかりつけの獣医師と相談しながら予防計画を立てることが、これまで以上に重要になってきていると考えられます。
また、フィラリア予防で意外と多いのが、「きちんと予防しているつもりだったが、実は抜けていた」というケースです。投与間隔が空いてしまったり、シーズンの始まりや終わりが曖昧になっていたりすると、知らないうちに感染のリスクが生じてしまいます。
フィラリアは完全に姿を消した存在ではなく、人の対策が緩めば、再び問題になり得る相手でもあります。だからこそ、フィラリアを、「今もきちんと向き合うべき寄生虫」として捉えつづけることが大切なのです。

[photo by Arnon]
古くて新しい寄生虫と、これからの向き合い方
フィラリアは、かつて多くの犬にとって身近な死因のひとつでした。しかし現在では、予防薬の普及により防げる病気になっています。この変化は、フィラリアそのものが弱くなったからではなく、人が正しく知り、対策を続けてきた結果です。
一方で、最新の研究が示しているように、フィラリアは決して過去の存在ではありません。イヌ科動物とともに長い進化の歴史を歩んできた寄生虫であり、気候変動や人の行動に、今も影響を受け続けています。環境が変われば、寄生虫もまた変わり得る存在です。
だからこそ、フィラリアを「もう心配しなくていい病気」としてしまわずに、「今もきちんと向き合うべき寄生虫」として捉え続けることが大切なのだと思います。毎年の予防をしっかり続けること、犬に合った薬を選ぶこと(MDR1遺伝子変異をもつ犬は注意が必要な場合があります)、そして迷ったときには獣医師に相談すること、これらひとつひとつが、犬の健康を守るための確かな積み重ねになります。
フィラリア予防は特別なことではありませんが、確実に犬の未来を変えてきた医療のひとつです。夏本番を迎える前に、あらためて予防の準備を整えておきたいところです。
【参考文献】
【関連記事】


