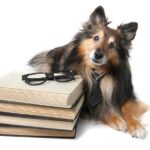文:尾形聡子

[Image by Kevin Seibel from Pixabay]
同じように体に負荷を受けても、なぜか回復の早い人がいる、そんなふうに感じたことはありませんか? あるいは、家庭内でインフルエンザが蔓延しても、なぜか決まって「この子は回復が早い」というようなことも少なくないでしょう。
そのような、体の内部や外部環境の変化に対して、体の恒常性(ホメオスタシス)や機能を維持する力のことを「ロバスト性(robustness:ロバストネス)」といいます。今回は、高齢犬におけるロバスト性を主軸として調査した、新しい視点をもたらしてくれる研究を紹介したいと思います。
ロバスト性とは?
ロバスト性という概念は、そもそも工学やシステム理論におけるもので、外乱や変動に対しても機能や構造を保つ性質のことをいいます。それが生物学や人の医学・老化研究の領域でも使われるようになりました。
生物学では、遺伝子発現や発達過程が環境変動や突然変異に左右されずに正常な形を保つこと、すなわち「強靭な生命システム」のことを指します。一方で医学や老化研究では、ストレス(手術・薬物負荷・感染など)があっても身体が回復し、加齢によっても機能や予備力を維持できる状態を意味します。
つまり、「ロバスト性」は老化研究領域での「フレイル(虚弱;健康な状態と要介護状態の間に位置し、身体機能や認知機能の低下が見られる状態)」と対をなす概念で、フレイルは「予備力低下・変化に対して崩れやすい状態」であるのに対し、ロバスト性は「予備力が高く、変化に対して安定している状態」とされています。ロバスト性が高いほど、フレイル耐性があるということになります。
フレイルという言葉が使われ始めたのもそう遠くないことです。それまでは「虚弱」や「老衰」といった言葉が使われていましたが、2014年に日本老年医学会が「フレイル」という学術用語の使用を提唱し、広く定着しました。
そこからフレイルという言葉を使用したあまたの人の老化研究が行われています。人に比べればまだまだ少ないものの、犬においても少しずつその影響が見られ始めており、犬曰くでもこれまでにいくつかの記事で犬のフレイル研究について紹介しています(フレイルに関する記事はこちらから→犬曰く「フレイル」記事一覧)。
ロバスト性は身体版レジリエンスと理解しよう
ロバスト性などという言葉で見るとちょっと難しく感じてしまうかもしれない方にぜひ伝えたいのは、ロバスト性は身体版レジリエンスのようなものであると理解していただきたいことです。
レジリエンスはもともと物理学の分野で使われていた言葉で、「ストレス(外から加わる力)に対抗する、いわば“跳ね返す力”」を意味します。それが生物学や心理学の分野において、たとえば天災を受けても生態系が回復したり、人や犬など個体の精神的な回復力を示す言葉として使われるようになっています(レジリエンスに関する記事はこちらから→犬曰く「レジリエンス」記事一覧)。
つまり、レジリエンスが主に精神面での回復力を示す言葉だとすると、ロバスト性は身体面での回復力を示す言葉になるということです。
さて、「ロバスト性」の意味、そしてその対にある「フレイル」の概念について理解していただけたでしょうか。説明はこのへんまでにしまして、高齢犬におけるロバスト性を調査した研究の紹介をしたいと思います。
この研究は人のフレイルにおける性差の謎(女性の方がフレイルになりやすいという傾向)を解き明かすことを目的として行われたものですが、非常に興味深い結果が出ていま